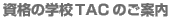���i�̊w�ZTAC �� �Љ�ی��J���m�^�|�C���g�`�F�b�N���b�Z�[�W�o�b�N�i���o�[
����������������������������������������������������������������������
�������@�@���i�̊w�Z�s�`�b�@�Љ�ی��J���m�u��
�����@�@�@�R�O�������I�@�|�C���g�`�F�b�N���b�Z�[�W�@��R�O���@2016/08/26
����������������������������������������������������������������������
�{���̂b�n�m�s�d�m�s�r================================================
�k�P�l�|�C���g�`�F�b�N�@��R�O��@�@����
�k�Q�l�������b�Z�[�W ��R�O��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�a�J�E�V�h�E�r�܁E���l�Z�@�����{�Ȑ��o�������ʐM�u���@�S���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���@�N�_�@�u�t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�t���@�c�����@��A���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�k�R�l�֓������w�@�����@���ւ̌��t ���̂P�O
======================================================================
����������������������������������������������������������������������
�@��30��@�@����
����������������������������������������������������������������������
�@��v�������ڂ̂����A�e�Ȗڂɂ����Ċ��Ɍf�ڂ��Ă��镔���ɂ��ẮA
�ȗ����Ă���ӏ�������܂��B
======================================================================
�@�J��@
======================================================================
�����N�ی��@�̉����ɔ�������
�@���N�ی��@�̉����ɔ����A�N���L���x�ɒ��̒����Ƃ��ĘJ�g����Œ�߂�
���Ƃ��ł���������A�u���N�ی��@��40���P���ɋK�肷��W����V���z
��30���̂P�ɑ���������z�i�T�~�����̒[���͐؎̂āA�T�~�ȏ�10�~����
�̒[����10�~�ɐ؏グ�j�v�Ƃ��ꂽ�B
======================================================================
�@���q�@
======================================================================
���O���o�^�������������@�֓�
�@���{�����Ɏ�������L���Ȃ��O���ɗ��n����@�ւɂ��āA�O���o�^����
���������@�ցA�O���o�^���\�����@�ցA�O���o�^�ʌ���@�֖��͊O���o�^
�^������@�ւƂ��āA�o�^���邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ��ꂽ�B
======================================================================
�@�J�Еی��@
======================================================================
���Љ�ی����t�Ƃ̕����ɌW�钲�����̉���
�@���a�i�⏞�j�N�����͋x�Ɓi�⏞�j���t�ƁA����Ɠ���̎��R�Ɋ�Â�
��Q�����N�������������ꍇ�̒��������u0.88�v�Ƃ��ꂽ�B
�����i�⏞�j���t�̏���z���̉���
�@���i�⏞�j���t�̏���z�y�эŒ�ۏ�z���A���̂悤�ɉ������ꂽ�B
�E����z�c�펞���104,950�~�A�������52,480�~
�E�Œ�ۏ�z�c�펞���57,030�~�A�������28,520�~
======================================================================
�@�ٗp�ی��@
======================================================================
���ٗp�p�����t�̎x���\���̉���
�@�ٗp�p�����t�i���N��ٗp�p����{���t���A���N��ďA�E���t���A�玙
�x�Ƌ��t���A���x�Ƌ��t���j�̎x���\���ɂ��āA�����Ƃ��āA
��ی��҂����Ǝ���o�R���čs�����̂Ƃ��ꂽ�B
���x�ƊJ�n�������ؖ����̒�o�����̉���
�@�x�ƊJ�n�������ؖ����̒�o�������A��ی��҂��玙�x�Ƌ��t���i
�m�F�[�E�i����j�玙�x�Ƌ��t���x���\�������͉��x�Ƌ��t���x���\����
�̒�o��������܂łƂ��ꂽ�B
�@
======================================================================
�@�����@
======================================================================
���ٗp�ی����̉���
�@�ٗp�ی�������������A����28�N�x�ɂ�����ٗp�ی����́A���̂Ƃ����
���ꂽ�B
�@�E��ʂ̎��Ɓ@�@1000����11
�@�E�_�ѐ��Y�Ɠ��@1000����13
�@�E���Ɓ@�@�@�@1000����14�@
======================================================================
�@�J����ʏ펯
======================================================================
���J���Ҕh���@
�@������J���Ҕh�����ƁE��ʘJ���Ҕh�����Ƃ̋敪�̔p�~
�@�@�]���A�J���Ҕh�����Ƃ́A��ʘJ���Ҕh�����Ɓi�����j�Ɠ���J����
�@�h�����Ɓi�͏o���j�ɋ敪����Ă������A���̋敪���p�~����A
�@�J���Ҕh�����Ƃ����ׂċ����Ƃ��邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@���h�����Ԃ̐������Ȃ��Ɩ��ɌW�����
�@�@�]���A�h���\���Ԃ̐������Ȃ��Ɩ��Ƃ��Đ��߂�26�Ɩ�����߂��
�@�Ă������A���̋Ɩ��̋敪��p�~���A26�Ɩ��ɊY�����邩�ǂ���
�@�ɂ������Ȃ��A�h���\���Ԃ̐������Ȃ��J���Ҕh���̋K�肪
�@�݂���ꂽ�B
�@�q�h���\���Ԃ̐������Ȃ��J���Ҕh���̗�r
�@�@�E�����ٗp�h���J���ҁi���Ԃ��߂Ȃ��Ōٗp�����h���J���ҁj�ɌW��
�@�@�@�J���Ҕh��
�@�@�E�ٗp�̋@��̊m�ۂ����ɍ���ł���h���J���҂ł����Ă��̌ٗp�̌p����
�@�@�@��}��K�v������ƔF�߂�����̂Ƃ��Č����J���ȗ߂Œ�߂��
�@�@�@�i60�Έȏ�̎ҁj�ɌW��J���Ҕh���@�c�@��
�@���h���掖�Ə��P�ʂ̘J���Ҕh���̎�����Ԃ̐���
�@�@�h���\���Ԃ��R�N�Ƃ���A�܂��A�ӌ�������Ԃɉߔ����J���g�����̈ӌ�
�@�����Ƃɂ��A�R�N������A�h���掖�Ə������Ƃ̋Ɩ��ɂ��āA
�@�h���\���Ԃ��������邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@���h���J���Ҍl�P�ʂ̘J���Ҕh���̎�����Ԃ̐���
�@�@�h���掖�Ə����́u�g�D�P�ʁv�̋Ɩ��ɂ��ẮA�h���\���Ԃ���������
�@�ꍇ�ł����Ă��A�u����̔h���J���҂�̑g�D�P�ʁv�Ɉ��������R�N��
�@�����Ď���Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂƂ��ꂽ�B
�@���J���_��\���݁E�݂Ȃ����x�̑n��
�@�@�h���悪�A���Ɍf���邢���ꂩ�̍s�ׂ��s�����ꍇ�ɂ́A���̎��_�ɂ����āA
�@�h���悪�h���J���҂ɑ��A���̎��_�ɂ�����J�������Ɠ���̘J����������e
�@�Ƃ���J���_��̐\���݂��������̂Ƃ݂Ȃ����ƂƂ��ꂽ�B�������A�h���悪
�@���̍s�����s�ׂ����̂����ꂩ�ɊY�����邱�Ƃ�m�炸�A���A�m��Ȃ�����
�@���Ƃɂ��ߎ����Ȃ������i�P�Ӗ��ߎ��j�Ƃ��́A���̌���łȂ��Ƃ��ꂽ�B
�@�@(1)�@�h���J���҂�h���֎~�Ɩ��ɏ]�������邱��
�@�@(2)�@�J���Ҕh�����Ƃ̋����Ă��Ȃ����Ǝ傩��J���Ҕh���̖�
�@�@�@�@ ���邱��
�@�@(3)�@�h���掖�Ə��P�ʂ̘J���Ҕh���̎�����Ԃ̐����̋K��Ɉᔽ����
�@�@�@�@ �J���Ҕh���̖̒��邱�Ɓi�h���\���Ԃ̉����ɌW��ߔ���
�@�@�@�@ �J���g�����ɑ���ӌ��̒���̎葱�̂������̂��̂��s���Ȃ�����
�@�@�@�@ �ɂ��ᔽ���邱�ƂƂȂ����Ƃ��������j
�@�@(4)�@�h���J���Ҍl�P�ʂ̘J���Ҕh���̎�����Ԃ̐����̋K��Ɉᔽ����
�@�@�@�@ �J���Ҕh���̖̒��邱��
�@�@(5)�@�J���Ҕh���@���͘J����@���̓K�p�Ɋւ�����ᓙ�̋K��ɂ��K�p
�@�@�@�@ �����@���̋K��̓K�p��Ƃ��ړI�ŁA�������̑��J���Ҕh���ȊO��
�@�@�@ ���ڂŌ_���������A�J���Ҕh���_��ɒ�߂�ׂ��������߂��ɘJ����
�@�@�@ �h���̖̒��邱�Ɓi������U���������̏ꍇ�j
�����N��Ҍٗp����@
�@���V���o�[�l�ރZ���^�[�̎戵�Ɩ��͈̔͂̌�����
�@�@�V���o�[�l�ރZ���^�[���s���L���̐E�ƏЉ�Ɩ��͘J���Ҕh�����Ƃɂ�����
�@�戵�Ɩ��͈̔͂́A�]���A��������̂���u�Վ��I���Z���I�Ȃ��́v����
�@���Ԑ���̂���u�y�ՂȋƖ��v�Ɍ����Ă������A�����ɂ��A�s���{���m����
�@�w�肵���Ǝ�y�ѐE��ɂ��ẮA��������y�ю��Ԑ���̂Ȃ��u�\�͂����p��
�@�čs���Ɩ��v�Ƃ��āA���̑ΏۂɊ܂܂�邱�ƂƂ��ꂽ�B
����Q�Ҍٗp���i�@
�@���ړI�̉���
�@�@��Q�Ҍٗp���i�@�́A�g�̏�Q�Җ��͒m�I��Q�҂̌ٗp�`�����Ɋ�Â�
�@�ٗp�̑��i���̂��߂̑[�u�A�ٗp�̕���ɂ������Q�҂Ə�Q�҂łȂ���
�@�Ƃ̋ϓ��ȋ@��y�ёҋ��̊m�ە��тɏ�Q�҂����̗L����\�͂�L���ɔ�������
�@���Ƃ��ł���悤�ɂ��邽�߂̑[�u�A�E�ƃ��n�r���e�[�V�����̑[�u���̑�
�@��Q�҂����̔\�͂ɓK������E�ƂɏA�����Ɠ���ʂ��Ă��̐E�Ɛ����ɂ�����
�@�������邱�Ƃ𑣐i���邽�߂̑[�u�𑍍��I�ɍu���A�����ď�Q�҂̐E�Ƃ̈���
�@��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂Ƃ��ꂽ�B
�@����Q�҂ɑ��鍷�ʂ̋֎~
�@�@���Ǝ�́A�J���҂̕�W�y�э̗p�ɂ��āA��Q�҂ɑ��āA��Q�҂łȂ���
�@�Ƌϓ��ȋ@���^���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ��ꂽ�B
�@�@�܂��A���Ǝ�́A�����̌���A����P���̎��{�A���������{�݂̗��p���̑���
�@�ҋ��ɂ��āA�J���҂���Q�҂ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��āA��Q�҂łȂ��҂�
�@�s���ȍ��ʓI�戵�������Ă͂Ȃ�Ȃ����̂Ƃ��ꂽ�B
�@�������I�z���̒�
�@�@�u���Ǝ�́A�J���҂̕�W�y�э̗p�ɂ��āA��Q�҂Ə�Q�҂łȂ��҂Ƃ�
�@�ϓ��ȋ@��̊m�ۂ̎x��ƂȂ��Ă��鎖������P���邽�߁A�J���҂̕�W
�@�y�э̗p�ɓ������Q�҂���̐\�o�ɂ�蓖�Y��Q�҂̏�Q�̓����ɔz������
�@�K�v�ȑ[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���Ǝ�ɑ��ĉߏd�ȕ��S��
�@�y�ڂ����ƂƂȂ�Ƃ��́A���̌���łȂ��v�Ƃ��ꂽ�B
�@�@�u���Ǝ�́A��Q�҂ł���J���҂ɂ��āA��Q�҂łȂ��J���҂Ƃ̋ϓ���
�@�ҋ��̊m�ۖ��͏�Q�҂ł���J���҂̗L����\�̗͂L���Ȕ����̎x��ƂȂ���
�@���鎖������P���邽�߁A���̌ٗp�����Q�҂ł���J���҂̏�Q�̓�����
�@�z�������E���̉~���Ȑ��s�ɕK�v�Ȏ{�݂̐����A�������s���҂̔z�u���̑���
�@�K�v�ȑ[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���Ǝ�ɑ��ĉߏd�ȕ��S��
�@�y�ڂ����ƂƂȂ�Ƃ��́A���̌���łȂ��v�Ƃ��ꂽ�B
�@�������̉���
�@�@�O�L�u��Q�҂ɑ��鍷�ʂ̋֎~�v�y�сu�����I�z���̒v�̘J�g�Ԃ�
�@�����ɂ��āA�s���{���J���ǒ��ɂ�鏕���A�w�����͊����i�����̉�����
�@�����j�̑ΏۂƂ��ꂽ�B
�@�@�O�L�u��Q�҂ɑ��鍷�ʂ̋֎~�v�y�сu�����I�z���̒v�̘J�g�Ԃ�
�@�����i�J���҂̕�W�y�э̗p�ɂ��Ă̕����������B�j�ɂ��āA��������
�@�ψ���ɂ�钲��̑ΏۂƂ��ꂽ�B
���E�Ɣ\�͊J�����i�@
�@���W���u�E�J�[�h�̕��y
�@�@���́A�J���҂̐E�Ɛ����v�ɑ����������I�ȐE�Ɣ\�͂̊J���y�ь����
�@���i���邽�߁A�J���҂̐E���̌o���A�E�Ɣ\�͂��̑��̘J���҂̐E�Ɣ\�͂�
�@�J���y�ь���Ɋւ��鎖���𖾂炩�ɂ��鏑�ʁi�E���o�L�^�����W���u�E
�@�J�[�h�j�̗l�����߁A���̕��y�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ��ꂽ�B
�@���L�����A�R���T���^���g���x�̖@�艻
�@�@�u�L�����A�R���T���e�B���O�v�ɂ��āA�u�J���҂̐E�Ƃ̑I���A
�@�E�Ɛ����v���͐E�Ɣ\�͂̊J���y�ь���Ɋւ��鑊�k�ɉ����A�����y�юw����
�@�s�����Ƃ������v�ƒ�`�����ƂƂ��ɁA�L�����A�R���T���^���g�́A�L�����A
�@�R���T���^���g�̖��̂�p���āA�L�����A�R���T���e�B���O���s�����Ƃ��Ƃ�
�@����Ƃ���A�L�����A�R���T���^���g���x���@�艻���ꂽ�B
======================================================================
�@���ۖ@
======================================================================
���ی������i����j
�@����̓���ی�������1000����36.7�ɕύX�i�����O��1000����38.3�j
�@�i���ϕی������A���ی������͕ύX�Ȃ��j
���W���̏���̒e�͓I�����̉����E�W���̏���̉��蓙
�@�W���̏���̉���̍ہA���̔N�̂R/31�ɂ����āA�����̕W�������̍ō���
���ɊY������(��)���̓����ɂ�����(��)�����ɐ�߂銄����100����0.5�i����
�O��100���̂P�j��������Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɁB
�@�W���������R�����lj������50���i139���~�j�܂łɁk�����O�͑�47���i121
���~�j�܂Łl�B
�@�W���ܗ^�z�̔N�x�v�z�i����j��573���~�ɁB�i�����O��540���~�j
���H���×{�W�����S�z���̉���
�@�H���×{�W�����S�z��460�~�ɁB�i�����O��260�~�j�iH28.4.1�`H30.3.31�܂�
��360�~�j�������A�w���a���ғ��ɂ��Ă�260�~�ɐ��u���k�����×{�W����
�S�z�i���@��Â̕K�v���������ҁj�ɂ��Ă�����|�̉�������l�B
���Љ��Ȃ��̑�a�@��f���̕��S�`����
�@�u��ʕa���̐���500�ȏ�̒n���Îx���a�@�v�y�сu����@�\�a�@�v�́A�I
��×{�Ɋւ����̋��z�ȏ�̎x�������҂ɋ��߂邱�Ƃ��`���t����ꂽ�B
�����Ґ\�o�×{�̑n��
�@���҂���̐\�o���N�_�Ƃ���V���ȕی��O���p�×{�̎d�g�݂Ƃ��āA���Ґ\
�o�×{���n�݂��ꂽ�B
���������t�̌�����
�@���C�O�×{��̎x���葱�̉���
�@�@�C�O�×{�ɌW��×{��̐\�����̒�o�ɓ�����A�u�C�O�ɓn�q����������
�@�m�F�ł��鏑�ށi�����A�q�j�̎ʂ��v�y�сu�C�O�×{�̓��e�ɂ��ė�
�@�{�S���҂ɏƉ�邱�ƂɊւ��铯�ӏ��v��Y�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�
�@���ꂽ�B
�@�����a�蓖���E�o�Y�蓖���̉���
�@�@���a�蓖���E�o�Y�蓖���̊z�́A�u�x���J�n���ȑO12���Ԃ̕W���̕��ϊz�v
�@�~1/30�~2/3�Ōv�Z�B
�@�@�x���J�n���ȑO�̒��߂ɕW������߂��Ă��錎��12�������̏ꍇ�́A�u��
�@�̇@�A�A�̂������Ȃ��z�v�~2/3
�@�@�x���J�n���ȑO�̒��߂̌p�������e���̕W�����ϊz�~1/30
�@�A�x���J�n�N�x�̑O�N�x9/30�ɂ�����S(��)�̕W�����ϊz��W���̊�b�Ƃ�
�@�@���V���z�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��̕W���~1/30
����ʕی������͈̔͂̉���
�@���ۂ̈�ʕی������ɂ��āA30/1000�`130/1000�i�����O��120/1000�j�̔�
�͓��Ō��肷����̂Ƃ��ꂽ�B
�����ɕ⏕���͈̔͂̉���
�@����ۂ̍��ɕ⏕���ɂ��āA130/1000�i�����O��164/1000�j�`200/1000
�͈͓̔��ɂ����Đ��߂Œ�߂銄���Ƃ��ꂽ�B�i�����̊ԁA������164/1000�j
�����茒�N�ی��g���Ɋւ������
�@�����茒�ۑg���̔F�ɌW��v���̊ɘa
�@�@���茒�ۑg���̔F�v���̂����A�u����ސE(��)�������ɂ킽�葊������
�@���܂�邱�Ɓv�u����ސE(��)�ł���ׂ����͈̂̔͂����������Ȃ���
�@�Ɓv���폜����A���茒�ۑg���̋K��̕ύX�ɂ�����ސE(��)�̐V�K����
�@�̗}�����\�ɁB
�@������ސE(��)�̕W��
�@�@����ސE(��)�̕W���ɂ��ẮA���茒�ۑg�����Ǐ�����O�N9/30�ɂ���
�@�����ސE(��)�ȊO�̑S(��)�̓����̕W�����ϊz�͈͓̔��ɂ����ċK��Œ�
�@�߂��z��W���̊�b�ƂȂ��V���z�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��̕W���Ƃ��邱�ƂɁB
�����̑��̉���
�@���Љ�ی��f�Õ�V�x��������ւ̎����̈ϑ�
�@�@�×{��A�o�Y�玙�ꎞ���A�Ƒ��o�Y�玙�ꎞ���A���z�×{��A���z��썇
�@�Z�×{��̎x���Ɋւ��鎖�����ɂ��ẮA�Љ�ی��f�Õ�V�x���������
�@���ۘA����Ɉϑ��ł��邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@���l�̗\�h�E���N�Â���Ɍ������C���Z���e�B�u�̋���
�@�@�ی��҂������҂ɑ��ė\�h�E���N�Â���̃C���Z���e�B�u������
�@�g�͏d�v�ł��邱�Ƃ���A�ی����ƂƂ��āu���N�Ǘ��y�ю��a�̗\�h�ɌW��
�@��ی��ғ��̎����w�͂ɂ��Ă̎x���v���ی��҂̓w�͋`�������ɒlj�����
�@���B
======================================================================
�@���N�@
======================================================================
���ی����W
�@�������N���ی���
�@�@����28�N�x�̍����N���ی����z�F16,260�~�i16,660�~�~0.976�j
�@�@����29�N�x�̍����N���ی����z�F16,490�~�i16,900�~�~0.976�j
���N���z�̉���
�@�����藦�E��N�x�Ȍ���藦
�@�@����27�N���ς̑S������ҕ����w���̑ΑO�N��ϓ������{0.8���A���ڎ��
�@������ϓ������|0.2���ƂȂ������߁A����28�N�x�̐V�K�ْ�҂̉��藦�y��
�@���ْ�҂̉��藦�i��N�x�Ȍ���藦�j�́A��������P����Ƃ��ĉ���
�@����A0.999�Ƃ��ꂽ�B�Ȃ��A����28�N�x�̔N���z����ɂ����ẮA�}�N���o
�@�σX���C�h�ɂ�钲���͍s���Ȃ��B
�@���N���z
�@�@��b�N���i���z�j�i���j�@�F780,100�~�i780,900�~�~0.999�j
�@�@�q�̉��Z�z�i��Q�q�܂Łj�F224,500�~�i224,700�~�~0.999�j
�@�@�q�̉��Z�z�i��R�q�ȍ~�j�F 74,800�~�i 74,900�~�~0.999�j
�@�����i�P���j�̔N���z�́A�Q���̊z��1.25�{
���S�z�Ə��\���̎�����x�̑n��
�@���J��b����w������w��S�z�Ə��\�������戵�҂́A�S�z�Ə��v���Y
��(��)������̈ϑ����āA�S�z�Ə��\�������邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ��ꂽ�B
�Ȃ��A�S�z�Ə��v���Y��(��)�����w��S�z�Ə��\�������戵�҂ɑS�z�Ə��\��
�̈ϑ��������Ƃ��́A�ϑ��������ɁA�S�z�Ə��\�������������̂Ƃ݂Ȃ����B
����[�ی����̔[�t
�@�ߋ��T�N�Ԃ̕ی�����[�t���邱�Ƃ��ł���V���Ȍ�[���x���n�݂��ꂽ
�iH27.10.1����H30.9.30�܂ł̎����[�u�j�B
�����莖�R�ɌW��ی����̔[�t�̓���
�@���莖�R�i����������蓙�̎��R�j�ɂ�荑�N�ی����̔[�t�@����킵����
�F�߂���ꍇ�A����I�ɓ���ی����̔[�t�����s���邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@���Ⴆ�A���莖�R�ɂ��ی����S�z�Ə��̎葱���ł��Ȃ��������Ƃ�\��
�@�@�o�A���J��b�����F����A�\�o�����������Ȍ�A�\�o���Ԃ́u����S�z
�@�@�Ə����ԁv�Ƃ����i�V��̎��҂����̐\�o���s�����ꍇ�A�\�o����
�@�@������N���z�����肳���j�B�܂��A�u����S�z�Ə����ԂƂ݂Ȃ��ꂽ��
�@�@�ԁv���̒ǔ[�Ώۊ��Ԃ�L����|��\���o�A���J��b�����F����A���Y
�@�@���Ԃɂ��Ēǔ[���\�B
������t���ی����̔[�t��
�@H26.3�ȑO�ɁA�t���ی����̔[�t���[�����܂łɍs��ꂸ�A�t���ی����̔[�t
���ނ̐\�o���������̂Ƃ݂Ȃ��ꂽ���Ԃ�L����҂́A���J��b�̏��F����
���F���O10�N�ȓ��̊��ԁi����t���Ώۊ��ԁj�̊e���ɂ��u����t���ی����v
��[�t���邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ��ꂽ�B
��������b�i���Œ��j�ւ̋��������ϔC�v���̌�����
�@�����ȕی����ؔ[�҂ɑ��鍑�Œ��ւ̋��������ϔC�̗v���̂P�ł���u
�[�t�`���҂��w24���x���ȏ�̕ی�����ؔ[���Ă��邱�Ɓv�̑ؔ[�������u24
���v����u13���v�Ɉ���������ꂽ�B
�����̑��̉���
�@�����̏��f���𖾂炩�ɂł��鏑�ނ��Y�����Ȃ��ꍇ�̎戵���̉���
�@�@���f���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ł��鏑�ނ�Y���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��́A
�@���Y���f��������̂ɎQ�l�ƂȂ鏑�ނ�Y�t����Α���邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@���ꌳ���@�ɂ�����
�@�@��p�ҔN���ꌳ���ɔ����A�ꕔ�̋K��ɕK�v�ȕ���������ʑ������̉���
�@���s��ꂽ�B
======================================================================
�@���N�@
======================================================================
���N���z�̉���
�@���ĕ]�����̉���
�@�@����27�N���ς̑S������ҕ����w���̑ΑO�N��ϓ������{0.8���A���ڎ��
�@������ϓ������|0.2���ƂȂ������߁A����28�N�x�̐V�K�ْ�҂̍ĕ]�����y
�@�ъ��ْ�҂̍ĕ]�����i��N�x�Ȍ�ĕ]�����j�́A��������P����Ƃ�
�@�ĉ��肳�ꂽ�B�Ȃ��A����28�N�x�̔N���z����ɂ����ẮA�}�N���o�σX��
�@�C�h�ɂ�钲���͍s���Ȃ��B
�@���]�O�z���藦�̉���
�@�@�]�O�z���藦�́A���a13�N�S���P���ȑO�ɐ��܂ꂽ�҂ɂ��Ă�1.000�A��
�@�a13�N�S���Q���Ȍ�ɐ��܂ꂽ�҂ɂ��ẮA0.998�Ƃ��ꂽ�B�i�ύX�Ȃ��j
�@�������N���z���̉���
�@�@�����N���z���ɏ悸����藦�́A0.999�Ƃ��ꂽ�B�i�ύX�Ȃ��j
����p�ҔN���ꌳ��
�@���K�p���O�K��̉���
�@�@(��)���i�ɂ��āA���������ɌW��K�p���O�K�肪�폜���ꂽ�B
�@��(��)�̎��
�@�@���Ԕ�p�ғ��ł���(��)�ł��邩���������ł���(��)�ł��邩����ʂ���
�@���߂̎�ʁk��P���`��S�����N(��)�l���A�V���ɐ݂���ꂽ�B
�@�����{�@��
�@�@(��)�̎�ʂ��Ƃ̕ی����t�A��b�N�����o���̕��S�E�[�t���ɌW�鎖����
�@�]���ʂ莟�̎��{�@�ւ��s���B
�@�@��P�����N(��)�������J����b
�@�@��Q�����N(��)�����ƌ��������ϑg���A���ƌ��������ϑg���A����
�@�@��R�����N(��)���n�����������ϑg���A�S���s�����E�����ϑg���A����A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�����������ϑg���A����
�@�@��S�����N(��)�����{�����w�Z�U���E���ώ��ƒc
�@��(��)�̎�ʂ̕ύX�ɌW�鎑�i�̓��r
�@�@����̓K���ɂ����Ďg�p�����(��)�ɂ��āA(��)�̎�ʂɕύX��������
�@�ꍇ�ɂ́A(��)���i�̎擾�y�ёr���̋K��́A(��)�̎�ʂ��ƂɓK�p�B
�@���قȂ�(��)�̎�ʂɌW�鎑�i�̓��r
�@�@��Q�����N(��)�A��R�����N(��)�A��S�����N(��)�́A�����ɁA��P����
�@�N(��)�̎��i���擾���Ȃ��B
�@�@��P�����N(��)�������ɑ�Q�����N(��)�A��R�����N(��)�A��S�����N(��)
�@�̎��i��L����Ɏ������Ƃ��́A���̓��ɁA��P�����N(��)�̎��i��r���B
�@��(��)���Ԃ̌v�Z
�@�@���N(��)�̎��i�擾���ɓ��Y���i��r�����A����Ɍ��N(��)�̎��i���͍�
�@�N��(��)�k���N�̑�Q��(��)�������l�̎��i���擾�����ꍇ�A���̌��̍ŏI
�@���ɂ�����(��)���i�k���N��(��)�̎��i���܂ށl�݂̂łP�ӌ���(��)���Ԃ�
�@���邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@������c�����̍ݘV�̓K�p
�@�@����c�������ݘV�̓K�p�ΏۂȂ����B����ɂ����J��b���x������V��
�@�̎��҂́A����c�����ƂȂ����Ƃ��́A�V���ݐE�x����~�͂̒�o���K
�@�v�ƂȂ����B
�@��S12.4.1�ȑO���̎҂̍ݘV�̓K�p
�@�@70�Έȏ�ݘV�̓K�p���Ȃ�����S12.4.1�ȑO���̎҂��ݘV�̓K�p�ΏۂƂ�
�@�����B����ɂ��A�����̎҂��g�p���鎖�Ǝ�́u70�Έȏ��p�ҊY���E
�@�s�Y���́v���@�\�ɓ͂��o�邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@���ی������ɂ���
�@�@��Q���E��R�����N(��)�ɌW��ی�������H30.9����A��S�����N(��)�ɌW
�@��ی�������H39.4����183/1000�ɌŒ肳��邱�ƂƂȂ����B
�@����x���E�Y�O�Y��x�ƏI��������̐\�o
�@�@��P���E��S�����N(��)�́A���Ǝ���o�R���čs���B��Q���E��R�����N(��)
�@�́A���Ǝ���o�R�����A���ڎ��{�@�ւɐ\�o���s���B
�@���ی����t���錠���ْ̍�
�@�@���������ɌW��N�������N�@�ɂ����̂Ƃ��ꂽ���Ƃ���A�ی����t����
�@���錠���͎��҂̐����Ɋ�Â��āu���{�@�ցv���ْ肷�邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@���[�������ɂ���
�@�@����܂ł�100�~�P�ʁi50�~�����؎̂�50�~�ȏ�؏グ�j����P�~�P�ʁi50
�@�K�����؎̂�50�K�ȏ�؏グ�j�ɕύX���ꂽ�B
�@���Q�����x���̔N���̉��Z
�@�@�x���������Ƃ̎x���z�ɂP�~�����̒[�����������Ƃ��͂�����̂Ă�
�@���ƂƂ��ꂽ�B����ɂ�薈�N�R�����痂�N�Q���܂ł̊Ԃɂ����Đ�̂�
�@���[���̍��v�z�ɂ��ẮA�Q�����̎x���z�ɉ��Z���Ďx�������ƂƂ��ꂽ�B
�@���ސE����
�@�@���N��(��)���i�r�����ɘV���̎��҂ł������ꍇ�A���i�r�����N�Z�P
�@���o�ߓ��̑����錎����N���z�����肵�Ă������A�ސE�����������N�Z�P��
�@�o�ߓ��̑����錎����N���z�����肷�邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@���ݘV�i���ݘV�j
�@�u�O���ȑO���������������c�����ł��錎�v�����ݘV�̓K�p�ΏۂƂȂ錎
�@�Ƃ��ꂽ�ق��A�����ސE�҂̍ݘV��~�ɂ��āA�����ɍēx���N�̎��i�擾
�@���Ȃ������ꍇ�A�ސE���������̔N���ɂ��čݘV��~���s��Ȃ����ƂƂ�
�@�ꂽ�B
�@���Q�ȏ���Ԏ҂̘V��
�@�@�Q�ȏ���Ԏ҂ɌW��V���ɂ��āA�V���̎x���v���E�x���z�̋K���K�p
�@����ꍇ�́A��P���`��S�����N(��)���ԂɌW��(��)���Ԃ��ƂɓK�p�B
�@���x�������͌��N(��)���Ԃ��ƂɊe���{�@�ւ��s���B
�@���Q�ȏ���Ԏ҂̘V���ɌW������N���z
�@�@�Q�ȏ���Ԏ҂̘V���̊z�́A�Q�ȏ��(��)�̎�ʂɌW��(��)���Ԃ����Z���A
�@�P�̊��Ԃ�(��)���Ԃ݂̂�L������̂Ƃ݂Ȃ������N���z�̋K���K�p�B
�@���̏ꍇ�A�����N���z�́A���L�̗D�揇�ʂɊ�Â��D�揇�ʂ̍����P�̊���
�@�ɌW��(��)���Ԃ��v�Z�̊�b�Ƃ���V���̊z�ɉ��Z����B
�@�u�����N���z�̉��Z�J�n���ł������N���ɉ��Z�v���u�����̏ꍇ�͊z�v�Z��
�@��b�ƂȂ���N(��)���Ԃ������N���ɉ��Z�v���u���Ԃ̒����������ꍇ�A
�@��P������Q������R������S�����N(��)���ԂɊ�Â��N���̏����ɉ��Z�v
�@���Q�ȏ���Ԏ҂ɂ��āA�ꌳ����̘V��t�̎��i���ԓ��̔���ɂ�����
�@�@�Q�ȏ�̎�ʂɌW����Ԃ̍��Z�̉ۂɂ��Đ�������Ǝ��̂Ƃ���B
�@�@[���Z��������]
�@�@�E���ʎx���̘V���̎��i�v���i�P�N�j
�@�@�E�����N���z�A�U�։��Z�̉��Z�E��~���̊��ԗv���i����20�N�j
�@�@[���Z����Ȃ�����]
�@�@�E�����v���̓���i44�N�j
�@�@�E��z�����̏�������v�Z�A�o�ߓI���Z�̌����v�Z�i480���j
�@�@�E������҂̓���k40�i���q��35�j�Ȍ�15�N�`19�N�l
�@�@�E�D���̎x���J�n�N��̓���i������15�N�j
�@���Q�ȏ���Ԏ҂̘V���̎x���J�グ
�@�@�Q�ȏ���Ԏ҂ɂ��āA�P�̊��ԂɊ�Â��V���̎x���J�グ�����́A����
�@��ʂ̌��N(��)���ԂɊ�Â��V���ɂ��Ă̓��Y�����Ɠ����ɍs��Ȃ����
�@�Ȃ�Ȃ��B
�@���Q�ȏ���Ԏ҂̘V���̎x���J����
�@�@�Q�ȏ���Ԏ҂ɂ��āA�P�̊��ԂɊ�Â��V���̎x���J�����\�o�́A����
�@��ʂ̌��N(��)���ԂɊ�Â��V���ɂ��Ă̓��Y�\�o�Ɠ����ɍs��Ȃ����
�@�Ȃ�Ȃ��B
�@���Q�ȏ���Ԏ҂̏�����Ɋւ���x������
�@�@�F����ɂ����ĂQ�ȏ���Ԏ҂ł������҂ɌW�����y�я��̎x��������
�@���f���ɂ�����(��)�̎�ʂɉ����āA���{�@�ւ��s���B
�@���Q�ȏ���Ԏ҂̏���̊z
�@�@����̎��҂ł����āA�F����ɂ����ĂQ�ȏ���Ԏ҂ł��������̂ɌW
�@�����̊z�́A�Q�ȏ��(��)�̎�ʂɌW��(��)���Ԃ����Z���P�̊��ԂɌW��
�@(��)���Ԃ݂̂�L������̂Ƃ݂Ȃ��āA����̊z���v�Z����B
�@���Q�ȏ���Ԏ҂̈���Ɋւ���x�������i�Z���v���j
�@�@�Q�ȏ���Ԏ҂ł������҂̈⑰�ɌW��Z���v���̈���̎x�������ɂ���
�@�́u(��)�̎��S�v���x�����R�Ƃ�����̂ɂ��ẮA���S���ɌW����{�@�ցA
�@�u(��)�ł������҂�(��)���i�r����ɁA(��)�ł������Ԃɏ��f�������鏝�a
�@�ɂ�菉�f���N�Z�T�N�o�ߓ��O�Ɏ��S�v���x�����R�Ƃ�����̂ɂ��ẮA
�@���Y���f���ɌW����{�@�ցA�u�P�E�Q���̏���̎��҂̎��S�v���x����
�@�R�Ƃ�����̂ɂ��ẮA���Y����̎x�����R�ƂȂ�����Q�ɌW�鏉�f����
�@�W����{�@�ւ��s���B
�@���Q�ȏ���Ԏ҂̈���Ɋւ���x�������i�����v���j
�@�@�Q�ȏ���Ԏ҂ł������҂̈⑰�ɌW�钷���v���̈���ɂ��ẮA�e����
�@���N(��)���Ԃ��ƂɁi�e���{�@�ւ��j�x������B
�@���Q�ȏ���Ԏ҂̈���̊z�i�Z���v���j
�@�@�Q�ȏ���Ԏ҂ł������҂̈⑰�Ɏx������Z���v���̈���̊z�́A�����A
�@�e���̌��N(��)���Ԃ��ƂɘV���̊z�̋K��̗�ɂ��v�Z�z�̍��Z�z��3/4
�@�����z�Ƃ���B���̏ꍇ�A����̊z�̌v�Z��b�ƂȂ�(��)���Ԃ̌����̌v�Z
�@�́A�Q�ȏ���Ԏ҂ł�����(��)���Ԃ����Z���A�P�̊��ԂɌW��(��)���Ԃ̂�
�@��L������̂Ƃ݂Ȃ����ꍇ�ɂ�����(��)���Ԃ̌����Ƃ���B
�@���Q�ȏ���Ԏ҂̈���̊z�i�����v���j
�@�@�Q�ȏ���Ԏ҂ł������҂̈⑰�Ɏx�����钷���v���̈���́A�e���̌��N
�@(��)���Ԃ��ƂɌv�Z���x������A�P�̊��ԂɊ�Â�����̊z�́A�u�����z�v
�@�u�V���̎���L����65�Έȏ�̔z��҂̓���z�v�ɍ��Z�⑰��������
�@���ē����z�Ƃ���B
�@���Q�ȏ���Ԏ҂ɌW��N���̎x���̒����i�����j
�@�@�Q�ȏ���Ԏ҂ɌW��N���̓��������́A����̎�ʂ̌��N(��)���ԂɊ��
�@���N���Ԃł̂ݍs����B
�@���Q�ȏ���Ԏ҂ɌW��N���̎x���̒����i�ߌ땥�ɂ��Ԋҋ����ւ̏[���j
�@�@�Q�ȏ���Ԏ҂ɌW��N���̉ߌ땥�ɂ��Ԋҋ����ւ̏[���́A����̎�
�@�ʂ̌��N(��)���ԂɊ�Â��N���Ԃł̂ݍs����B
�@���q�ɑ������̎x����~
�@�@�z��҂�����̎x����~�̐\�o���s�����ꍇ�ł����Ă��A�q�ɑ�����
�@�̑S�z�����������x����~���邱�ƂƂ��ꂽ�B
��������b�i���Œ��j�ւ̋��������ϔC�v���̌�����
�@�����ȕی����ؔ[�҂ɑ��鍑�Œ��ւ̋��������ϔC�̗v���̂P�ł���u
�[�t�`���҂��ؔ[���Ă���ی������̑��@�̋K��ɂ�钥�����̊z���w�P���~�x
�ȏ�ł��邱�Ɓv�̑ؔ[�ی������̋��z���u�P���~�v����u�T�疜�~�v�Ɉ���
������ꂽ�B
======================================================================
�@�Љ�ی���ʏ펯
======================================================================
���ИJ�m�@
�@�Ј����P�l�̎ИJ�m�@�l�̐ݗ������\�ƂȂ����B
���������N�ی��@
�@�����ۑg���ɑ��鍑�ɕ⏕���̌�����
�@�@���ۑg���̗×{�̋��t���ɗv�����p���ɑ��鍑�ɕ⏕�̊����ɂ���
�@���S�\�͂ɉ��������S�Ƃ���ϓ_����A�����͂����Ă���H28�N�x�`H32�N�x
�@�ɂ����Ēi�K�I�Ɍ��������ƂƂ��A���������ɉ�����13������32���܂ł̔�
�@�͓��ɂ����Đ��߂Œ�߂銄���Ƃ��邱�ƂƂ����B
�@���ی����̊�b���ۊz�ɌW�镊�ی��x�z�̈��グ
�@�@��p�ҕی��̎d�g�݂Ƃ̃o�����X���l�����A���ۂ̕ی����i�Łj�̕�
�@�ی��x�z���i�K�I�Ɉ����グ���AH28�N�x�ɂ��ẮA��b���ۊz�ɌW�镊
�@�ی��x�z��52���~����54���~�ɁA�������Ҏx���������ۊz�ɌW�镊�ی��x
�@�z��17���~����19���~�Ɉ����グ�邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@�����ΓI�K�v���t���̎x������ւ̈ϑ�
�@�@�ی��҂́A���ΓI�K�v���t�y�єC�Ӌ��t�̎x���Ɋւ��鎖�����x�������
�@�ϑ����邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ��ꂽ�B
���D���ی��@
�@���a�ی������ɂ��āA1000����40����1000����130�i�����O��1000����110�j
�܂ł͈͓̔��ɂ����āA���肷����̂Ƃ��ꂽ�B
������҈�Êm�ۖ@
�@���\�h���N�Â���̑��i
�@�@�L��A�����s���悤�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����u(��)�̌��N�̕ێ�
�@���i�̂��߂ɕK�v�Ȏ��Ɓv�ɁA�u���N�Ǘ��y�ю��a�̗\�h�ɌW���ی��҂�
�@�����w�͂ɂ��Ă̎x���v��������ꂽ�B
�@���������Ҏx�����̑���V��
�@�@��p�ҕی��̌������Ҏx�����ɂ��āA��蕉�S�\�͂ɉ��������S�Ƃ�
�@��ϓ_����AH28�N�x���瑍��V���������R���̂Q�Ɉ����グ��ꂽ�B
�����ی��@
�@�����ȏ㏊���҂ɑ��镉�S�����̈��グ
�@�@���ȏ�̏���������65�Έȏ��(��)�ɂ��āA���p�ҕ��S�������Ƃ���
�@�Q���Ƃ��ꂽ�B
�@�����K�͒ʏ����̒n�斧���^�T�[�r�X�ւ̈ڍs��
�@�@�ʏ����̂������p�����19�l�����̏��K�͂Ȓʏ����ɂ��āA�n�斧
�@���^�ʏ����Ƃ��Ēn�斧���^�T�[�r�X�Ɉʒu�t�����邱�ƂƂ��ꂽ�B
======================================================================
�@�s���\���Ẳ���
======================================================================
���s���s���R���@�̉����ɔ����s���\���Ẳ���
�@�J�Еی��@�A�ٗp�ی��@�A���N�ی��@�A�����N���@�A�����N���ی��@�ɂ�����
���̏����ɌW��R�������ɂ��Ă͌����Ƃ��ĂR�������o�߂����Ƃ��A
�ĐR�������ɂ��Ă͌����Ƃ��ĂQ�������o�߂����Ƃ��́A���ꂼ�ꂷ�邱�Ƃ�
�ł��Ȃ����̂Ƃ��ꂽ�ق��A���v�̉������s��ꂽ�B
�@�܂��A�����@�ɂ��ẮA�����@�Ǝ��̕s���\���Ă̋K�肪�폜����A
���@�̏����ɌW��s���\���Ăɂ��ẮA�s���s���R���@�Ɋ�Â��s��
�i�����J����b�ɑ��ĐR�������j���ƂƂ��ꂽ�B�@
======================================================================
���{���̓|�C���g���i�邱�Ƃɏd�_��u���Ă��邽�ߕ\�L�͊ȗ������Ă����
�@�����������܂��B���m�ȕ\�L�ɂ��܂��Ă͂��莝���̋��ނɂĂ��m�F����
�@�肢���܂��B
======================================================================
�������u�|�C���g�`�F�b�N���b�Z�[�W�v�ŏI��̂����A������
�@
�@30���ԁA���t���������Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B�{�����O�P��
�Ԃ͂���܂Ŋw�K���Ă������e������ƂĂ��厖�Ȏ����ł��邽�߁A���J
�͎��̓��T�Ƃ��ă|�C���g�`�F�b�N���b�Z�[�W�̔z�M�����邱�Ƃɂ��A�d�v
�������Ċm�F���Ē������Ƃ��Ӑ}���Ă���܂����B
�@�����ł́A��₪�������o�肳��܂����A���̂悤�Ȗ��͑��̑����̎�
���҂����_�ł��Ȃ����Ƃ������A���ۂɗ^����e���͂���قǑ傫�����̂ł�
�Ȃ��Ǝv���܂��B���ɁA�u��{���v�͍��i���C���ɓ��B������̂قƂ��
���~�X�������ɓ��_���Ă���ł��傤�B
�@�{������O�ɂ�����x�S�Ȗڂ��������Ƃ��́A�ׂ����ӏ��̓T���b�Ɨ����A
�u��{�����̍Ċm�F�v�ɏd�_���������Ƃ��������߂��܂��B
�@����ł͍Ō�ƂȂ�܂����A�{���������͂���܂ł̊w�K�̐��ʂ𑶕��ɔ�
�����A�ǂ����ʂ��o����悤������Ă��������I
�@
�@�s�`�b�ꓯ�������Ă��܂��B
======================================================================
����������������������������������������������������������
�k�Q�l�������b�Z�[�W ��R�O��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�` �s�`�b�u�t�E�u�t����� �`
����������������������������������������������������������
���@�{���@�N�_�@�u�t�m�a�J�E�V�h�E�r�܁E���l�Z�@�����{�Ȑ��o������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐM�u���S���n
�@���悢��{�����ł��B�ْ����Ė���Ȃ��Ȃ�����Ȃ��ƌ������l����������
����������Ǝv���܂��B�����������O�ْ͋��Ŗ������Ȃ��������Ƃ��v��
�o���܂��B
�@�����A���܂�ْ���������Ǝ��͂��\���ɔ����ł��܂���ˁI
�@���܂ŁA���ꂾ���撣���Ă����������g�Ɏ��M�������čŌ�܂őS�͂Ŋ撣��
���������I
�@�{�����ł͌������Ƃ��Ȃ���肪�o�肳��邱�Ƃ����邩���m��܂���B
�i�I�����Łj�ł������ŏł�����_���ł���I�������Ƃ��Ȃ���肪�o�肳�ꂽ
���́A�w����ς肱��Ȗ��A�o�Ă����ȁx�Ə��Ă��������B
�@�����āA���̗͂��āA�傫���[�ċz���āE�E�C�����𗎂������Ă�����
���S�̂��������ƒ��߂Ă݂܂��傤�B�̃q���g�͂����Ɩ�蕶�̒��ɉB��
�Ă��܂�����ˁI
�@�Ō�̍Ō�܂Ő�ɒ��߂��Ɋ撣���Ă��������B
�@���i����ΐl���͕ς��I���͕K�������܂��I
�@�F����̍��i��S�������Ă��܂��B
���@�c���� ��[�u�t��]
�@�{�����܂ł��Ǝc��Q���B�ꂵ�݂Ȃ�����Ȃ�Ƃ������܂ŒH�蒅���܂����B
�����O�ŕs�����Ǝv���܂����A���܂Ő���t����Ă��܂�����ˁH�Ȃ�A
�ςݏグ�Ă����m���Ɏ��M�������Ė{�����ɗՂ݂܂��傤�B
�����M�����Ă��ɗ��������Ȃ����ց�
�@���ꎮ���́A�S�̂ς���ƁA�P��ɂ������鎞�Ԃ͂R���ł��̂ŁA
�킩��Ȃ���肪�����Ă����̖��ɌŎ������A�Ƃ肠������ɂ��Đ��
�i�݂܂��傤�B
�@�܂��A�킩����̂����̂����O�������Ȃ��Ă����̒��ɐ������������
���_�ł��܂����A�ɘ_����ƁA�ꎈ�����킩����̂��Ȃ��Ă����ꂪ������
�ł�����̖��͓��_�ł��܂��B
�@���̂悤�ɁA�ꎈ�ꎈ���ׂĂɐ��m�Ȓm����������Γ��_�ł��Ȃ��Ƃ���
���̂ł͂���܂���̂ŁA�͂݉߂��Ȃ��ő��v�ł��B
�@�����āA�I�������́A�m��Ȃ���肪�o�ē�����O���炢�̋C����������
�ėՂނ��Ƃ������^���ʂł͑厖�ł��B���������ɂ������ẮA�܂�����
���Ƃ��Ȃ����������Ȗ��͌�ɂ��Ă����͂킩���������
�I�������ɂ������莞�Ԃ������Ď��g�݂܂��傤�B
�@�������Ƃ��Ȃ����������Ȗ��́A�I�������O���[�s���O���āA
�����A�O��̂Ȃ���y�э��܂Őςݏグ�Ă����m������i�荞�ނ��Ƃ�
�\�Ȃ��̂�����܂��B������߂��ɍŌ�܂ł������Ă݂܂��傤�B
�@�����ʼn������b�Z�[�W�͏I�����܂����A�s�`�b�̍u�t�ꓯ���Ȃ���������
�����܂��B
�@11���̍��i���\�����S���ŏΊ炢���ς��ɂȂ邱�Ƃ�����Ă���܂��B
======================================================================
����������������������������������������������������������
�k�R�l�֓������w�@�����@���ւ̌��t ���̂P�O
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
10.�ƍN�ɂ́A�}�C�i�X��]���ăv���X�ɕς���̌����������������B
���̂��߁A�G�g�̍]�˂ւ̍��ւ̖��������e��邱�Ƃ��ł����B
����������������������������������������������������������������������
�@�L�b�G�g�́A���{�̐�Ό��͎҂ɂȂ����B�k������łڂ������c�������̘_��
��������ƍN���O�͂��爯(�A�V)�̐�����Ӌ��̍]�˂ւƍ��ւ𖽂����B
�@�ƍN�́A�����A���̖��ɏ]��Ȃ���A���ׂ���郊�X�N���������B���ɁA
�D�c�M���̓�j�A�D�c�M�Y�́A�G�g�̍��ւ̖��ɔw�������ߎ��ׂ��ꂽ�B
�@�����̉Ɛb�������钆�A�ƍN�͏G�g�̂��̖��������e�ꂽ�B����܂�
�ςݏd�˂Ă������Ƃ��[���ɂ��ꂽ���Ȃ����߁A�ƍN�͑ς����B�ƍN�͏�������
�납��l�������𑗂�A�}�C�i�X�̋t�����ɂ�����Ă��A�����Ē��߂��ɑς���
���v���X�ɓ]���閼�l�ł������B�ƍN�����̓����e�ꂽ���Ƃ���ԋ�����
��̂́A�G�g�ł������B
�@�ƍN�͏G�g�Ɂu�V�����̗��`�ҁv�Ǝv�킹�Ȃ���͂�~�ς��A�G�g���v����
�ƁA�փP���Ƒ��̐w�ł����Ƃ����ԂɖL�b�Ƃ�łڂ��A�V����D��������B
���̐����鎼�n�тɉ߂��Ȃ������֓�����i�]�ˁj�́A�ƍN���]�ˏ��z���A
������𓌑J���������ƂŖL���ȑ�n�֕ϐg�𐋂��A���E���w�̑�s��ɂȂ邱
�Ƃ��ł����B
�@�G�g�̖������́A���͌ォ��l����ƁA�ŗǂ̑I���ɂȂ����̂ł���B
=======================================================================
<<�����ǂ�育���A>>
�{���ŁA�R�O���Ԃ̃|�C���g�`�F�b�N���b�Z�[�W�����ׂďI���ƂȂ�܂��B
�����ǂ��������A���肪�Ƃ��������܂����B
���̊�悪�A�����ł��F���܂̂����ɗ��ĂĂ���K���ł��B
�Ȃ��A�{���������Q�X��(��)�ɂ́A�u�|�C���g�`�F�b�N���b�Z�[�W�������v��
�z�M����\��ł��B�{�����́u����v��u�����v�̂��m�点��
�����ē������Ă��������܂��̂ŁA��낵�����肢�������܂��B
���āA���悢��{�������߂Â��Ă܂���܂����B���ꂩ��{�����܂ł̊�
�́A����܂ł̊w�K�̐��ʂ��\�ɔ������邽�߂ɂ��A�̒��Ǘ��ɓw��
�Ă��������B�����āA�|�C���g�`�F�b�N���b�Z�[�W�����p���āA��{����
�̊m�F�ɗ͂𒍂��ł��������B
�s�`�b�́A�ИJ�m���̊F���ܑS����S���牞�����Ă��܂��B
�F���܂̖��������邢���̂ƂȂ�܂��悤�A�u�t�E�s�`�b�Ј��ꓯ�S���
���F�肵�Ă���܂��B�{�����A������Ă��������I�I
-- �s�`�b�Љ�ی��J���m�u�� --
=======================================================================
�y�|�C���g�`�F�b�N���b�Z�[�W �o�b�N�i���o�[ �f�ڊ����̂��m�点�z
�C���^�[�l�b�g��́u�|�C���g�`�F�b�N���[���o�b�N�i���o�[�v�Ɋւ��܂��ẮA
�W��31��(��)�Ō��J�I���Ƃ����Ă��������܂��B�������������������B
���|�C���g�`�F�b�N���b�Z�[�W�o�b�N�i���o�[
http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/sharosi_pointcheck.html
=======================================================================
���i�̊w�Z�s�`�b�@�@http://www.tac-school.co.jp/
Copyright(C)2016 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.
���f�ڋL���̖��f�]�ځA�]���A���ҁA�ҏW������؋ւ��܂��B
���s�`�b�Љ�ی��J���m�u���z�[���y�[�W
http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/
��101-8383
�����s���c��O�蒬3����2��18��
�s�`�b�������