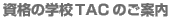資格の学校TAC > 社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー
┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋╋┻ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第22号 2016/08/18
┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第22回 厚生年金保険法(3)
〜 遺族厚生年金・厚生年金基金等 〜
〔2〕応援メッセージ 第22回
新宿校・町田校・横浜校 担当 竹之下 節子 講師 より
======================================================================
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
第22回 厚生年金保険法(3)
遺族厚生年金・厚生年金基金等
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
======================================================================
遺族厚生年金
======================================================================
●被保険者等要件
○短期要件
(1)被保険者の死亡
(2)資格喪失後に、被保険者期間中に初診日がある傷病により、その初診日
から起算して5年を経過する日前に死亡
→「喪失後5年を経過する日前」とするのは×(H18)
(3)障害等級「1,2級」の障厚の受給権者の死亡(3級含まず)(H23,26)
※(1)(2)の場合は保険料納付要件を満たす必要あり(H19,22,26)
原則:納付済+免除が全期間の3分の2以上
特例:H38.4.1前に死亡日があるときは、死亡日の属する月の前々月まで
の1年間に滞納なし(死亡日に65歳未満の者に限る。)(H21)
-----------------------------------------------------------
○長期要件
(4)老厚の受給権者又は受給資格期間を満たした者の死亡
●遺族の範囲
○配偶者・子・父母・孫・祖父母であって、死亡当時「生計維持」あるもの
・夫・父母・祖父母は55歳以上(ただし、「遺基」の受給権を有する夫を
除き60歳まで支給停止)(H18,24,27)
・子・孫は18歳年度末の到達前 or 20歳未満で障害等級1,2級(3級は
18歳年度末まで)の状態にあり、かつ、現に婚姻していないこと
※兄弟姉妹は含まない。
○配偶者と子は同順位
・「子」の遺厚…「配」が受給権を有する間は支給停止(原則)(H18,22,26)
・「配」の遺厚…子と生計を同じくしないために「子」のみが遺基の受給
権を有する間は支給停止(原則)
※労災と異なり失権後に次順位者が受給権を取得すること(転給)はない。
(H23)
●年金額
○〔老厚×3/4〕相当額(原則)
※短期要件の場合 … 被保険者期間の300月保障あり(H26)
※長期要件の場合 … 給付乗率(5.481/1000、7.125/1000)の読替えあり
(H22,27)
○65歳以上の「配偶者」で老厚の受給権を有する者
次の(1)及び(2)のいずれか高い方の額とし、その額から受給権者自身の「老
厚」の額を控除した額が、実際の遺厚の支給額となる。
(1) 遺厚の額=〔老厚×3/4〕相当額
(2)〔(1)の遺厚の額×2/3〕+〔受給権者の老厚×1/2〕
※「配偶者」が同一の支給事由に基づく遺基の支給を受けるときは、(1)
の額とする。
○65歳以後の遺厚(配偶者「以外」で老厚の受給権を有するもの)
遺厚の額(〔老厚×3/4〕相当額)から、その者の老厚の額を控除した額が
実際の支給額となる。(H22)
●厚生年金保険の年金額計算のまとめ
【老厚】【遺厚(長期)】 給付乗率の読替えあり、300月保障なし
【障厚】【遺厚(短期)】 給付乗率の読替えなし、300月保障あり
●中高齢寡婦加算
○加算対象
・受給権取得当時子のない妻…受給権取得当時40歳以上65歳未満
(H19,22,27)
・受給権取得当時子のある妻…40歳到達時に子と「生計同一」
○加算額 …遺基の3/4相当額(H21)
○加算期間…受給権取得時(受給権取得当時子がある場合は、遺基が支給さ
れなくなったとき)から65歳到達まで
●経過的寡婦加算
〇「S31.4.1以前生まれ」の妻は、65歳到達後に経過的寡婦加算が行われるこ
とあり(H27)
※中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算のいずれも、「遺基」を受けることがで
きる間は支給停止
※「障基+遺厚」の併給の場合、経過的寡婦加算は停止
●若年妻の失権事由(5年経過後失権)(H19)
○遺厚の受給権取得時30歳未満の妻が遺基の受給権ない場合
→遺厚の受給権取得日から起算して5年を経過したときに失権(H26)
○遺厚と遺基の受給権を有する妻が30歳到達日前に遺基の受給権消滅
→遺基の受給権消滅日から起算して5年を経過したときに失権(H23)
●子又は孫の失権事由(H19)
---横断整理---
○社保(国・厚)の遺族年金
死亡後18歳年度末までの間に障害の状態(障害等級1,2級に該当)と
なった場合、18歳年度末では失権せず、20歳到達(20歳到達前に障害の
状態に該当しなくなったときはそのとき)まで受給権者となる。
→障害等級3級に該当する場合には、18歳年度末で失権(H22,27)
○「労災」の遺族(補償)年金
労働者の「死亡後」に障害の状態になっても、18歳年度末で失権
======================================================================
脱退一時金
======================================================================
●被保険者期間が「6月以上」ある「日本国籍」を有しない者(国年の被保険
者でないものに限る)が次の要件を満たすときに請求できる。(H18,24)
・老厚の受給資格期間を満たさない(H26)
・障厚等の受給権を有したことがない(H26)
・「日本国内に住所」を有しない(H20)
・最後に「国民年金の被保険者」の資格を喪失した日(同日に国内に住所を
有する者にあっては住所を有しなくなった日)から起算して2年経過して
いない(H18,26)
※「厚年」の資格喪失日起算2年以内ではない。
※「日本国籍を有する者」には支給されない。(H18)
●脱退一時金の額 = 平均標準報酬額(再評価率は乗じない) × 支給率(H26)
○支給率=〔最終月の属する年の前年10月保険料率×1/2×一定の数〕(H27)
○最終月…最後に被保険者資格を喪失した日の属する月の前月
※最終月が1月〜8月までのときは、前々年10月の保険料率を用いる。
○一定の数は被保険者期間の区分による
6月以上12月未満…6
:
36月以上 …36(H20)
●脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった被保険者で
あった期間は被保険者でなかったものとみなす。
======================================================================
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)
======================================================================
●制度開始(施行日)
合意分割…平成19年4月1日
3号分割…平成20年4月1日
●分割対象となる期間
合意分割…施行日(H19.4.1)より前の婚姻期間を対象期間に含む。(H21)
3号分割…施行日(H20.4.1)より前の婚姻期間は特定期間に含まない。(H26)
●分割方法
合意分割…第1号改定者(標準報酬の多い方)から第2号改定者(少ない方)へ
3号分割…特定被保険者から被扶養配偶者へ
●分割割合
合意分割…当事者の合意(合意に至らないときは家庭裁判所)により定める。
※50%を上限(H21,27)
3号分割…2分の1(合意不要)(H26)
●手続き
合意分割…当事者の合意による請求(原則)
3号分割…被扶養配偶者による請求(合意不要)
※特定被保険者が障厚(特定期間の「全部」が年金額の計算の基礎になっ
ているものに限る。)の受給権者であるときは、3号分割は行わない。
※特定期間の「一部」が障厚の額の計算の基礎となっているときは、その
期間を除いて3号分割の請求をすることができる。
●共通事項及び注意事項
○請求期限…原則として、離婚成立等翌日から起算して2年(H21,26)
○年金受給権者の場合…請求月の「翌月」から改定(H19,20,26)
○効力…請求のあった日から「将来に向かってのみ」その効力を有する。
●みなし被保険者期間の扱い(以下、「離婚時みなし被保険者期間」「被扶養
配偶者みなし被保険者期間」ともに「みなし被保険者期間」と表記)
○被保険者期間の月数に算入しない場合
・定額部分の計算(H24)
・老厚(老基)の受給資格期間(25年以上)
・特別支給の老厚(60歳台前半の老厚)の支給要件〔(被)期間1年以上〕
(H19,24,27)
・長期加入者の特例(44年以上)
・加給年金額の支給要件となる(被)期間の月数(原則240月)(H24)
・脱退一時金の要件(6月以上)
○被保険者期間の月数に算入する場合
・報酬比例部分の計算
・本来支給の老厚(65歳以後の老厚)の支給要件〔(被)期間1月以上〕
○その他
・遺厚の支給要件(長期要件)(H19,24)
※過去に厚生年金保険の被保険者であったことがない者が死亡した場合
であっても、その者が、みなし被保険者期間を有し、かつ、老厚の受
給権者又は受給資格期間を満たしたものであるときは、厚生年金保険
の被保険者であった者の死亡として、遺厚が支給されることがある。
・振替加算された老基の受給権者が、みなし被保険者期間を含めて240月以
上の老厚を受けることができることとなったときは、振替加算は行われ
なくなる。(H19)
・300月最低保障が行われた障厚の受給権者については、みなし被保険者期
間は障厚の額の計算の基礎としない。(H19)
・合意分割・3号分割により改定(決定)された標準賞与額は、在職老齢年
金の額の算定基礎となる総報酬月額相当額の計算の基礎としない。(改定
前のものを基礎とする)(H22)
======================================================================
厚生年金基金
======================================================================
●存続厚生年金基金
H25改正法施行前に設立された厚生年金基金であって、施行日(H26.4.1)以後
において存続するもの(以下「基金」という。)
※施行日以後は新たな厚生年金基金の設立は認めない。
●加入員
〇設立事業所に使用される第1号厚生年金被保険者
〇加入員となった月にその資格を喪失した者は、資格を取得した日にさかの
ぼって、加入員でなかったものとみなす。
●給付
○法定給付…老齢に関し年金(老齢年金給付)、脱退に関し一時金を支給する。
○任意給付…「死亡又は障害」に関し、年金給付又は一時金給付を行うこと
ができる。
※死亡又は障害に関する給付は、基金に支給を義務づけたものではない。
○基金が支給する給付を受ける権利は、基金が裁定する。
●掛金
〇老齢年金給付の額の計算の基礎となる各月につき徴収
〇事業主と加入員が折半負担(原則)
※基金は、事業主の掛金の負担割合を増加することができる。
→事業主「又は加入員」の負担割合を増加できる、とするのは×(H20)
●通常解散(H20)
○解散理由
(1) 代議員定数の3分の2以上の多数による議決
(2) 事業継続不能
(3) 厚労大臣の解散命令
※(1)(2)によるときは厚労大臣の認可を要する。
○基金が解散したときは、政府が責任準備金相当額を徴収
●特例解散制度(H26.4.1から起算して5年を経過する日までの時限措置)
○自主解散型基金
「自主解散型基金」
・・・代議員定数の3分の2以上の多数による議決等を理由に解散(自主解
散)しようとする日において年金給付等積立金の額が責任準備金相当
額を下回ると見込まれるもの
「責任準備金相当額の減額」
・・・自主解散型基金は、厚労大臣に責任準備金相当額の減額を可とする旨
の認定を申請することができる。
「自主解散型納付計画」
・・・自主解散型基金及び設立事業所の事業主は、自主解散型納付計画を作
成し、厚労大臣の承認を受けることができる。
○清算型基金
「清算型基金」
・・・事業の継続が著しく困難と認められ、業務運営上相当の努力をしてい
る基金を、清算型基金として厚労大臣が指定
「清算計画の承認」
・・・清算型基金は、清算計画を作成し、厚労大臣の承認を受けなければな
らない。→厚労大臣の承認を受けた日に解散
「責任準備金相当額の減額」
・・・清算計画の承認申請の際に、責任準備金相当額の減額を可とする旨の
認定を申請することができる。
「清算型納付計画」
・・・清算計画の承認申請の際に、清算型基金及び設立事業所の事業主が清
算型納付計画を作成し、厚労大臣の承認を受けることができる。
======================================================================
※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
======================================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔2〕応援メッセージ 第22回
〜 TAC講師陣・講師室より 〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■ 竹之下 節子 講師[新宿校・町田校・横浜校担当]
私は受験生のとき「ああもう、勉強するのはいやだ!」と途中で何度も考え
ました。こんな苦しいことは、早く終わりにしてゆっくりしたい、遊びたいと
思っていました。
でもあのころは充実していました。
睡眠不足だの時間がないだの、何だかんだ言いながらも、私は気力にあふれ
ていました。
それを証明するかのように、本試験が終わるとやることがなくなって、空気
の抜けた風船のような「ふぬけ」になってしまいました。
皆さんは今、つらいとお感じかもしれませんが、実はとても価値のある
「試練」の中にいらっしゃいます。どうか存分に、受験生の「大詰めのとき」
を味わってください。
皆様の合格を、心から応援しております。
=======================================================================
いかがでしたか?
本試験まで残り10日。頑張ってくださいね!
=======================================================================
資格の学校TAC http://www.tac-school.co.jp/
Copyright(C)2016 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。
◆ポイントチェックメッセージバックナンバー
http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/sharosi_pointcheck.html
◆TAC社会保険労務士講座ホームページ
http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/
〒101-8383
東京都千代田区三崎町3丁目2番18号
TAC株式会社