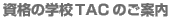資格の学校TAC > 社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー
┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋╋┻ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第20号 2016/08/16
┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第20回 厚生年金保険法(1)
〜 適用等・本来支給の老齢厚生年金 〜
〔2〕応援メッセージ 第20回
池袋校 担当 市川 則欣 講師
津田沼校 担当 藤代 輝雄 講師より
======================================================================
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
第20回 厚生年金保険法(1)
適用等・本来支給の老齢厚生年金
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
======================================================================
適用等
======================================================================
●適用、被保険者、標準報酬
※健保と厚年は共通事項が多いので、覚えるときのポイントは健保との違い
を掴むこと。主な違いは次の通り。
【健保】 【厚年】
○船 舶---------- 適用除外 適用あり
○年齢等上限 ---- 後期高齢者該当 70歳未満(※高齢任意加入あり)
○標準報酬月額等級 1級 5.8万円 1級 9.8万円
(最高等級)50級 139万円 30級 62万円(H21)
○標準賞与額上限-- 年度累計573万円 1回 150万円(H24)
○標準報酬月額の等級区分の改定
〔健保〕「最高等級の被保険者の割合が全体の1.5%を超える」状態続く
〔厚年〕「『標準報酬月額の平均額×2』が最高等級の額を超える」状態
続く(H23)
●任意単独被保険者(70歳未満)
○適用事業所「以外」の事業所に使用される70歳未満の者(H19)
○「事業主の同意」→「厚労大臣の認可」により任意加入(H19,24)
※同意した事業主には、保険料の半額負担と納付の義務が生ずる。
(H19,24)
※「70歳」に達したときには「その日」に資格喪失(H27)
※「厚労大臣の認可」により任意に資格喪失可能(事業主の同意は不要)
(H27)
※高齢任意加入と異なり「老齢」年金の受給権取得は資格喪失事由ではな
い。
●高齢任意加入被保険者(70歳以上)
○適用事業所「以外」の事業所に使用される高齢任意加入被保険者
・「事業主の同意」→ 厚労大臣の「認可」により任意加入(H25,26)
※同意した事業主には、保険料の半額負担と納付の義務が生ずる。
※「老齢」年金の受給権者は、高齢任意加入することができない。
→「障害」年金受給権者は高齢任意加入できない、とするのは×(H21)
○適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者
・実施機関への「申出」により任意加入(H20)
※適用事業所の場合、「認可」は不要
・事業主同意なし → 被保険者本人が保険料の全額負担 & 納付義務(H24)
・事業主同意あり → 事業主は、保険料の半額負担と納付の義務(H24)
※事業主は、被保険者の同意を得て、上記同意を将来に向かって撤回する
ことができる。当該「撤回」により資格を喪失することはない。(H19)
○主な資格喪失事由・喪失日
・死亡 → 死亡日の翌日
・使用されなくなった → その日の翌日
・老齢基礎年金等の受給権取得 → その日の翌日
・適用事業所「以外」の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪
失の申請に対する厚労大臣の「認可」 → 認可日の翌日
※事業主の同意不要
・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失の「申出」受理
→ 受理日の翌日
※事業主の同意不要
・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者本人が保険料の全額負担・
納付の場合であって、保険料を督促状の指定期限までに納付しないときは、
「納期限の属する月の前月末日」喪失(H27)
→「督促状の指定期限の翌日に喪失」とするのは×
※本人が保険料の全額負担・納付の場合であって、初めて納付すべき保険
料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しない場合は、「高
齢任意加入被保険者とならなかった」ものとみなされる。
→「指定期限の翌日に喪失」とするのは×(H20)
●70歳以上の使用される者
○該当・不該当日、報酬月額、賞与に関する事項の届出要(H19,20,21,23)
※70歳以上の使用される者については高在老の仕組みを適用(H23,27)
※保険料は徴収しない。
======================================================================
第1号厚生年金被保険者に係る保険料等
======================================================================
●第1号厚生年金被保険者に係る保険料率(平成27年9月〜平成28年8月)
○第1種,2種 … 178.28/1000
○第3種 … 179.36/1000
※基金の加入員は上記の率から免除保険料率を控除(H18)
●育休等期間中の保険料の免除(H23)
○「3歳」到達までの育休中又は育休に準ずる措置期間
※「介護」休業期間については免除の対象とはならない。
○免除は、「育休等開始日の属する月」から開始
→ 育休等開始月の「翌月」からとするのは×
→「申出日の属する月」からとするのは×
○育休等「終了日の翌日が属する月の前月」まで免除
※終了予定日前に終了するときは、終了後「速やかに」届出
→「あらかじめ」届出、とするのは×(H20)
○免除期間は被保険者期間に算入し、保険料納付済期間として扱う。
●産前産後休業期間中の保険料の免除
○出産日(出産日が出産予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎は98
日)から出産日後56日までの間に労務に従事しない期間
※「妊娠又は出産に関する事由」を理由とする場合に限る。
○免除は「産前産後休業開始日の属する月」から開始
→ 休業開始月の「翌月」からとするのは×
→「申出日の属する月」からとするのは×
○産前産後休業「終了日の翌日が属する月の前月」まで免除
○免除期間は被保険者期間に算入し、保険料納付済期間として扱う。
●保険料の納付期限は「翌月末日」(H22)
○高齢任意加入被保険者の納付期限も「翌月末日」
======================================================================
本来支給の老齢厚生年金(65歳以後の老齢厚生年金)
======================================================================
●支給要件(H20,24)
○被保険者期間「1月」以上
※特別支給の老厚(60歳台前半の老厚)は「1年」以上
○65歳以上
○老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしている。
●失権事由は「死亡」のみ
※特別支給の老厚は、「65歳到達」でも失権
●年金額(報酬比例部分の額)の計算
「 平均標準報酬額(月額) × 給付乗率 × 被保険者期間の月数 」
※計算をする際は、H15年3月までの期間と、H15年4月以降(総報酬制導
入により「賞与」を年金額に反映)に分けて計算したものを合算する。
○「平均標準報酬額(月額)」
H15年3月以前 … 平均標準報酬「月額」(標準報酬月額の平均)
H15年4月以後 … 平均標準報酬「額」(標準報酬月額・標準賞与額の平均)
※実際の計算の際は再評価率を用い、過去の標準報酬月額等に一定の率を
乗じて計算する。
○「給付乗率」
H15年3月以前 … 7.125/1000
H15年4月以後 … 5.481/1000
※S21.4.1以前生まれの者は、生年月日により読替えあり
○被保険者期間の「月数」
※H15年3月以前とH15年4月以後に分ける。
※月数の上限はない。→定額部分の額の計算とは異なる。
※第3種被保険者であった期間は、4/3倍、6/5倍する場合あり
→国年の老基の額の計算と異なることに注意
●経過的加算
「 定額部分相当額 −基礎年金相当額 」
○定額部分相当額 =「1,628円 × 改定率 × 被保険者期間の月数」(H20)
※「1,628円」は生年月日により「1.875〜1」を乗じる。
※被保険者期間の月数には生年月日に応じた「上限」あり
S 4.4.1以前 420月(35年)(H21)
S 4.4.2〜S 9.4.1 432月(36年)
S 9.4.2〜S19.4.1 444月(37年)(H22)
S19.4.2〜S20.4.1 456月(38年)
S20.4.2〜S21.4.1 468月(39年)
S21.4.2以後 480月(40年)(H25)
→「生年月日にかかわらず、480が上限」とするのは×(H20)
○「基礎年金相当額」
※基礎年金相当額を計算するときの「厚年(被)期間」は、S36.4以後の20
歳以上「60歳」未満の厚年(被)期間(実月数)である。(H18,19)
→「生年月日に応じた乗率を乗じて得た月数」とするのは×(H18)
●加給年金額の加算
○老齢厚生年金(被保険者期間月数が原則240以上)の「受給権取得当時」、
「生計を維持」していた配偶者・子があるときに加給年金額を加算
・「65歳未満」の配偶者(T15.4.1以前生まれの者は年齢制限なし)
・子(18歳年度末まで or 20歳未満で障害等級「1,2級」の状態)(H19)
※子の障害等級は「3級」含まず
※子が18歳年度末経過後に障害等級1,2級に該当しても、加給年金額の
対象外(H18,21,22)
※受給権取得当時被保険者期間の月数が240未満であっても、「退職改定」
により240以上となったときは、240以上となるに至った当時生計を維
持する配偶者・子がいるときには加算されることがある。
○中高齢の特例に該当するときは、240未満でも要件を満たす。(H26)
●加給年金額 (H21,26)
○配偶者及び1子・2子 … 224,700円×改定率
○3子以降 … 74,900円×改定率
●配偶者加給年金額の特別加算
昭和9.4.2以後生まれの「受給権者」に加給年金額加算対象配偶者があるとき
※特別加算額は、遅く生まれた受給権者ほど金額が大きい。(H19,25)
※特別加算額は、「配偶者」の生年月日ではなく、「受給権者」の生年月日
により金額が決まる。
※「子」については特別加算なし
●加算対象不該当による年金額の改定
○加算対象者が「不該当理由」に該当した月の翌月から年金額を改定
(H18,26,27)
○不該当理由 … 加算対象者の死亡、生計維持状態がやむ
配偶者65歳、離婚等
子の婚姻、18歳年度末、障害状態の子が20歳等
●加給年金額の支給停止 … 次のいずれかに該当するときは支給停止
○配偶者が、加入期間が原則240月以上の老齢厚生年金等の支給を受けること
ができるとき(H22)
※配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けるときであっても、加給年金
額は支給停止されない。(H19)
○配偶者が、障害厚生年金等の支給を受けることができるとき(H26)
○子の加算額が加算された障害基礎年金との併給の場合、老齢厚生年金に係
る子の加給年金額を停止(H18,19,24)
●高在老
「総報酬月額相当額+基本月額」が支給停止調整額を「超える」ときに、超
えた額の2分の1相当に12を乗じて得た額(支給停止基準額)の支給を停止
(H22,27)
「 支給停止基準額 =
(総報酬月額相当額+基本月額−支給停止調整額)× 1/2 × 12 」
○総報酬月額相当額(H25)
標準報酬月額+〔以前1年間の標準賞与額の総額〕× 1/12
○基本月額(H25)
〔老齢厚生年金の額−(加給年金額+繰下げ加算額+経過的加算額)〕× 1/12
○支給停止調整額 … 47万円(H23)
※支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額、繰下げ加算額及び経過的
加算額を除く)以上のときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額及び経過
的加算額を除く)の支給を停止(基本年金額と加給年金額が支給停止)
(H22,24,26)
※老基は在職老齢年金の仕組みにより支給停止されず、全額支給される。
(H24)
※70歳以上の使用される者にも「高在老」の適用あり(H23)
●繰上げ、繰下げの老基と老厚との関係
○繰上げ … 同時に請求を行わなければならない。(H27)
○繰下げ … 老厚のみ or 老基のみ単独で申出を行うことができる。(H19)
※特別支給の老厚を受給していた者も支給繰下げの申出できる。(H19)
●年金額の改定
○総報酬月額相当額が改定されたことによる在職老齢年金の改定(当月改定)
(H20)
※総報酬月額相当額が改定された「翌月」から改定ではない。(H27)
○資格喪失による改定(退職改定)… 資格喪失後、被保険者となることな
くして1月を経過したときは、退職日等から起算して「1月経過日の属
する月」から改定(H20,23,26)
※資格を喪失した「月前」における被保険者であった期間を計算の基礎と
して年金額を改定
======================================================================
※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
======================================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔2〕応援メッセージ 第20回
〜 TAC講師陣より 〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■ 市川 則欣 講師[池袋校担当]
社会保険労務士直前の学習について、受験生の方にワンポイントアドバイス
をしたいと思います。試験直前になればなるほど、あれもまだ、これもやらな
くてはと気が焦り、やみくもに新しい参考書や問題集に手を出してしまう受験生
の方がいますが、それはかえって自分自身の不安を煽ることになりかねません。
今まで利用してきたテキストや教材、問題集を信じて、新しいことを覚えるより
も、直前期だからこそ、かえって基本事項を徹底的に見直し、反復学習すること
が合格への近道と信じて下さい。今まで自分が勉強してきたことに自信を持ち、
最後まで決してあきらめない気持ち、これが一番の試験攻略法です。
ぜひ、その気持ちを持って試験に臨んでください。
■ 藤代 輝雄 講師[津田沼校担当]
試験本番まで残すところ2週間足らずとなりました。暑い日が続く中、最後
の詰めの努力をしていることでしょう。カレンダーを見ては焦り、まだまだ足
らないところがあるのではと不安にかられる毎日だと思います。
私が3年目にしてようやく合格したときもそうでした。それこそ試験の前の晩
などは気持ちが昂ぶってなかなか眠りにつけず、1時間ほどの睡眠時間で試験会
場に向かったものでした。しかし、試験会場に着いたころには、勉強をやり切っ
た思いが満ちてきて自信をもって試験問題に取り組むことができました。
最後の最後まで努力し続けた人には、必ず結果がついてきます。
合格を祈っています。
=======================================================================
いかがでしたか?
本試験まで残り12日。頑張ってくださいね!
=======================================================================
資格の学校TAC http://www.tac-school.co.jp/
Copyright(C)2016 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。
◆ポイントチェックメッセージバックナンバー
http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/sharosi_pointcheck.html
◆TAC社会保険労務士講座ホームページ
http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/
〒101-8383
東京都千代田区三崎町3丁目2番18号
TAC株式会社