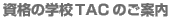資格の学校TAC > 社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー
┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋╋┻ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第7号 2016/08/03
┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第7回 労災保険法(2)
〜 保険給付(2)〜
〔2〕応援メッセージ 第7回
水道橋校・新宿校・大宮校担当 明田 修 講師
名古屋校担当 安藤 直樹 講師より
======================================================================
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
第7回 労災保険法(2)
保険給付-2
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
=====================================================================
障害(補償)給付
=====================================================================
●障害(補償)給付は、業務上又は通勤による傷病が治ゆし、身体に障害が存す
る場合に、労働者の請求に基づいて行う。
○障害(補償)年金 1級(313日分)〜7級(131日分)(H18)
○障害(補償)一時金 8級(503日分)〜14級(56日分)
●併合
「同一の事故による身体障害が2以上」あるときは、原則として重い方の等
級とするが、13級以上の障害が2以上のときは次のとおり。(H21)
○「13級以上」が2以上…重い方を「1級」繰上げ
○「8級以上」が2以上…重い方を「2級」繰上げ
○「5級以上」が2以上…重い方を「3級」繰上げ(H20)
※「9級(391日)」と「13級(101日)」の場合は、合算した492日分を支給
●加重
既に身体障害のあった者が、「新たな」業務災害又は通勤災害により「同一
の部位」の障害の程度を重くした場合は、次の方法により給付額を算定。
○前後とも年金の場合
加重「後」の年金額 − 加重「前」の年金額
○加重前が一時金で、加重後が年金 (H21)
加重「後」の年金額 − 加重「前」の一時金の額の「25分の1」
○前後とも一時金の場合
加重「後」の一時金の額 − 加重「前」の一時金の額
※既に障害補償年金を受ける者は、加重後の障害等級に応ずる新たな障害補
償年金が支給され、従前の障害補償年金は支給されない、とするのは×
(H21)→差額支給による障害(補償)年金と、既存の障害(補償)年金の両方の
受給権を有する。
●障害(補償)年金の受給権者の障害の程度が自然に変更した場合は、新たに該
当する障害等級に応ずる障害(補償)年金又は障害(補償)一時金が支給される
(H21)
※障害(補償)「一時金」を受給した者の障害の程度が「自然に変更」した場
合は、変更後の障害(補償)給付は支給されない。(H19)
●障害(補償)給付は「治ゆ後」の給付。傷病が再発した場合は障害(補償)年
金の受給権消滅。
●障害(補償)一時金受給者の傷病が「再発し、治ゆ後に障害が残った」ときは、
加重の取扱いに準じ差額支給を行う。
●障害(補償)年金前払一時金の額
障害等級別の最高限度額又は給付基礎日額の200、400、600、800、1,000、1,200
日分のうち、最高限度額の範囲内で受給権者が選択する額
○障害等級別の最高限度額 1,340日分 (1級)〜560日分 (7級)
●障害(補償)年金前払一時金は、同一事由につき「1回」に限り請求できる。
(遺族(補償)年金前払一時金も同様)
※同一の事由につき、一定額を限度として「複数回請求することができる」
「一定期間経過後に再度受けることができる」とするのは×(H20)
●障害(補償)年金前払一時金の請求は、原則として、障害(補償)年金の請求と
同時。
ただし年金の支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する
日までの間は、年金請求後でも請求できる。(遺族(補償)年金前払一時金も同様)
●障害(補償)年金前払一時金の支給を受ける権利は「2年」で時効消滅。
(遺族(補償)年金前払一時金も同様)
●障害(補償)年金差額一時金は、労働者の死亡当時その者と
(1)「生計を同じくしていた」配・子・父・孫・祖・兄
(2)「生計を同じくしていなかった」配・子・父・孫・祖・兄
のうち先順位の者に支給される。
=====================================================================
介護(補償)給付
=====================================================================
●介護(補償)給付を受給することができるのは、障害等級・傷病等級「2級」
以上の一定の障害の状態にある障害(補償)「年金」の受給権者又は傷病(補
償)年金の受給権者である。(H25)
※障害(補償)「給付」の受給権者とするのは×(障害(補償)一時金を含んで
いるため)
※「3級」以上、「障害の程度にかかわらず」とするのは×(H21)
●常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に常時又は随時介護を受け
ていなければ支給されない。
●一定の障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している間や病院・診
療所に入院している間は支給なし。(H18,24)
●「月」を単位として支給(H23)
●「常時」介護を要する状態にある場合の支給額
○104,950円を上限とする実費支給(H25)
○ 57,030円[親族等による介護を受けた日があるとき(支給事由が生じた月
を除く)の最低保障額]
●「随時」介護を要する状態にある場合の支給額
○ 52,480円を上限とする実費支給
○ 28,520円[親族等による介護を受けた日があるとき(支給事由が生じた月
を除く)の最低保障額]
●介護(補償)給付の請求先及び初回の請求時期(H21)
○所轄労基署長に請求
○障害(補償)年金の受給権者…当該年金の請求と同時、又はその請求後
○傷病(補償)年金の受給権者…当該年金の支給決定を受けた後
=====================================================================
遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)
=====================================================================
●遺族(補償)年金を受けることができる遺族(受給資格者)
○配・子・父・孫・祖・兄であって、労働者の死亡当時その者の収入により
「生計を維持」していたもの。(H18,19)
○遺族の順位は上記の順で、最先順位者が受給権者となる。(H18)
※生計維持が認められるには、「単に労働者と生計を一にしていただけでは
足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要」
とするのは×→ 生計の一部を維持されていれば足り、消費生活の大部分を
営んでいることは要しない。
※生計維持の認定は、労働者との同居の事実の有無、労働者以外の扶養義務
者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の定める
基準により行われる。
※重婚的内縁関係にあった場合の遺族(補償)給付の受給権者は、原則届出に
よる婚姻関係にあった者とする。ただし、届出による婚姻関係がその実体
を失って形骸化し、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがな
かった場合に限り、事実上の婚姻関係にあった者とする。(H18)
●妻以外の者については、次の者が受給資格者となる。(H19)
(1)一定の年齢(55歳以上or18歳年度末まで)
(2)障害(5級以上or労働に高度の制限を受ける等)の状態にある
※夫・父・祖・兄については「60歳以上」とするのは×(H19)
●55歳以上の「夫」・父・祖・兄が受給権者となったときは、60歳になるまで
支給停止。ただし、前払一時金は60歳に達する前であっても受給できる。
※「妻」については、年齢による支給停止はない。
●年金額は「受給権を有する遺族」と「その者と生計を同じくしている受給資
格者」の数による。
1人 … 153日分(55歳以上又は一定障害にある「妻」は175日分)
2人 … 201日分
3人 … 223日分
4人以上… 245日分
※覚えるときのポイント…「153」と「201」だけ覚える。
それぞれに「22」を足していくと残りの数字が導き出せる。
「153」+22→ 「175」(55歳以上等の妻1人のとき)
「201」+22→ 「223」(3人)+22 → 「245」(4人以上)
●遺族(補償)給付の受給権者が2人以上いる場合は、給付額を「受給権者」の
人数で除して得た額が1人あたりの受給額となる。(H22)
●遺族(補償)年金の受給権は、次の場合に消滅する。(H19,23)
(1)死亡したとき。
(2)婚姻をしたとき。
(3)直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき。
(4)離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
(5)18歳年度末が終了したとき(障害要件を満たす場合を除く)。
(6)障害の状態でなくなったとき(年齢要件を満たす場合を除く)。
●子等は、18歳年度末で受給権消滅となるが、労働者の「死亡当時から引き続
き」一定の障害の状態にあるときは、失権しない。
※この扱いは「国年」「厚年」(以下「社保」)の遺族年金と異なる。
社保では「死亡後」に障害となった場合であっても、18歳年度末の時点で
一定の障害状態にあれば、20歳(途中で障害の状態になくなったときは
その時点)まで失権しない。
●労働者の死亡当時「胎児」であった子が障害状態で出生したとしても「死亡
当時から引き続き」障害の状態とはされない。(H19)→18歳年度末で失権
●受給権者が1年以上行方不明となったときは、同順位者(ないときは次順位
者)の申請により所在不明の間、支給停止。(H18,27)
※「6か月以上」「遺族のいずれかの申請」、とするのは×
●遺族(補償)一時金の支給額は次のいずれかである。
・給付基礎日額の1000日分
・1,000日分 −(既に支給された年金・前払一時金の合算額)
●遺族(補償)一時金を受けるべき者の順位(H19,25)
(1)配偶者
(2)労働者の死亡当時その収入によって生計維持していた子・父・孫・祖
(3)(2)に該当しない(=生計維持していなかった)子・父・孫・祖並びに兄
※配偶者は生計維持関係の有無にかかわらず最先順位
※兄弟姉妹は生計維持関係の有無にかかわらず最後順位
※遺族(補償)一時金の受給権者は「一定の年齢」や「一定の障害」の状態で
あることを要しない。(遺族(補償)「年金」と異なる)
※遺族(補償)一時金を受けることができるのは、労働者の死亡当時その収入
によって生計を維持していた者に限られない。
●葬祭料(葬祭給付)は、労働者が死亡した場合に「葬祭を行う者」に支給。
※遺族(補償)給付を受けることができる遺族のうち最先順位者に支給、とす
るのは×
●葬祭料(葬祭給付)の額は、31万5千円+給付基礎日額の30日分(給付基礎日額
の60日分を最低保障)。(H18)
=====================================================================
二次健康診断等給付
=====================================================================
●二次健康診断等給付は、一次健康診断において、厚生労働省令で定める検査
項目のうち「いずれの項目にも」異常の所見があると認められるときに行わ
れる。(H23)
●二次健康診断等給付は、健診給付病院等(社会復帰促進等事業として設置され
た病院・診療所又は都道府県労働局長の指定する病院・診療所)において行う。
※健診給付病院等以外の病院で行われることはない。
●二次健康診断等給付は、一次健康診断を「受けた日」から3箇月以内に請求。
※一次健康診断の「結果を知った日」から3箇月以内、とするのは×(H21)
●二次健康診断等給付の請求書は、健診給付病院等を経由して「所轄都道府県
労働局長」に提出。(H19)
●二次健康診断等給付は、既に脳血管疾患・心臓疾患の症状を有する者には行
わない。(H25)
●二次健康診断等給付は、特別加入者には行わない。(H20,21)
●二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断につき1回
に限り行われる。(H25)
======================================================================
※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
======================================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔2〕応援メッセージ 第7回
〜 TAC講師陣より 〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■明田 修 講師[水道橋校・新宿校・大宮校担当]
本試験の前々日くらいまでは、睡眠時間を削って最後の追い込みをしましょう。
そして、前々日くらいからは、体調を整えるべく、しっかり睡眠もとりながら、
ほどほどに勉強してください。
それと、皆さんがそれぞれに自覚している苦手科目を優先して学習して下さい。
合格するためには、1科目でもいわゆる足切りラインを下回ってはならないから
です。
ご健闘をお祈りします。
■安藤 直樹 講師[名古屋校担当]
「社会保険労務士になりたい!」初めてそう思ったときの気持ちを思い出しま
しょう。今日までみなさんは並大抵ではない努力を積み重ねて来ています。
あと25日、学力はこれまでとは比べ物にならないほど伸びます。本試験当日ま
で絶対に伸び続けます。不安なときは、「今年、受かる!」と心の中で唱えて
みてくださいね。唱えた数だけ合格が近づくと私は思います。
努力が合格という集大成になるまで、ほんの一歩まで来ています!今の苦しみ
は、受験後に振り返ったときにきらきらとした思い出となり、揺るぎない自信に
なります。みなさんが社会保険労務士になって夢を叶えていかれますように。
=======================================================================
いかがでしたか?
本試験まで残り25日。頑張ってくださいね!
=======================================================================
資格の学校TAC http://www.tac-school.co.jp/
Copyright(C)2016 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。
◆ポイントチェックメッセージバックナンバー
http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/sharosi_pointcheck.html
◆TAC社会保険労務士講座ホームページ
http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/
〒101-8383
東京都千代田区三崎町3丁目2番18号
TAC株式会社